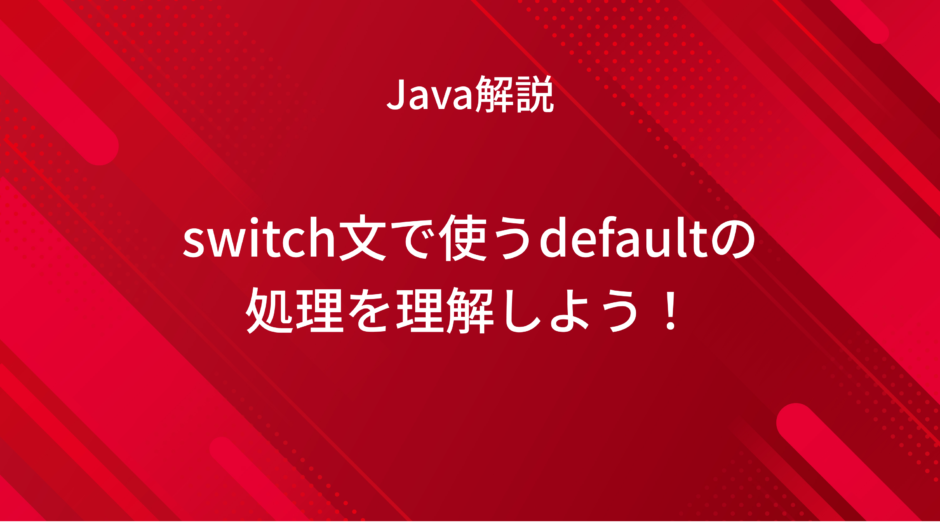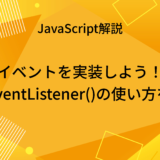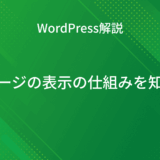この記事ではswitch文で使われるdefaultの使い方に焦点を当てて解説をしていきます!
switch文の詳しい書き方を解説している内容ではないので、ご了承ください。
記事の内容
- switch文のdefaultとは?
- defaultの処理の例
- defaultの記載位置
- まとめ
switch文のdefaultとは?
まずは結論からになります。
switch文のdefaultはcaseで指定したいずれの条件も満たさなかった時に実行したい処理を記載するために使います。
また、switch文の注意点にもなりますが、defaultはcaseの条件を満たしていたとしてもbreakがなければ実行されてしまいます。
ここからは具体的な例を見ていきましょう。
まずはdefaultの処理が行われない例です。
int num = 2;
switch (num) {
case 0:
System.out.println(“0です。”);
break;
case 1:
System.out.println(“1です。”);
break;
case 2:
System.out.println(“2です。”);
break;
case 3:
System.out.println(“3です。”);
break;
default:
System.out.println(“defaultの処理です。”);
}
// 実行結果
// 2です。このサンプルコードでは「2です。」とコンソール上に表示されます。caseの条件を満たしており、breakも記載されているため、正常に処理が行われます。
このようにcaseの条件が満たされている場合、defaultは実行されません。
defaultの処理の例
では次にdefaultの処理が実行されるコードを見ていきましょう。この記事では2つのケースを使ってみていきます。
【ケース1】
int num = 4;
switch (num) {
case 0:
System.out.println(“0です。”);
break;
case 1:
System.out.println(“1です。”);
break;
case 2:
System.out.println(“2です。”);
break;
case 3:
System.out.println(“3です。”);
break;
default:
System.out.println(“defaultの処理です。”);
}
// 実行結果
// defaultの処理です。このケースは caseにあるいずれの条件も満たしていないため、defaultの処理が実行されています。
【ケース2】
int num = 2;
switch (num) {
case 0:
System.out.println(“0です。”);
case 1:
System.out.println(“1です。”);
case 2:
System.out.println(“2です。”);
case 3:
System.out.println(“3です。”);
default:
System.out.println(“defaultの処理です。”);
}
// 実行結果
// 2です。
// 3です。
// defaultの処理です。このケースでは先ほどと違い、breakが抜けています。breakを書き忘れるのはswitch文が思った通りの動きをしてくれなくなるため注意しましょう。
breakが抜けていると、もしcaseの条件を満たしていたとしてもdefaultの処理が実行されます。
defaultの記載位置
defaultは通常可読性の観点からcaseの最後に書きますが、caseの前でも途中でもどこに書いても問題ないです。
int num = 4;
switch (num) {
case 0:
System.out.println(“0です。”);
break;
case 1:
System.out.println(“1です。”);
break;
case 2:
System.out.println(“2です。”);
break;
default:
System.out.println(“defaultの処理です。”);
break;
case 3:
System.out.println(“3です。”);
break;
}
// 実行結果
// defaultの処理です。このようにcaseの途中に書いても問題ないです。
ちなみにbreakを書き忘れるとdefault以下のcaseの処理も実行されてしまいます。
まとめ
今回はswitch文のdefaultについて解説をしてきました!
正しく使えるようにしていきましょう!
最後まで読んでいただきありがとうございます。
 いぬっころブログ
いぬっころブログ